top of page


コシボソヤンマとシラタマタケ
11月8日、先週は出張で上川町方面の緑地へ、2度出かける機会がありました。多摩丘陵では ほとんど見られない低山地性の動植物が多く、訪れる度に良い出会いが待ち受けています。 薄暗い沢筋の高さ6mくらいのスギの枝先に、大型のトンボが止まりました。双眼鏡で見ても よくわからないくらいの距離です。崖をよじ登り、何とか全身を捉えることができました。 腹部第3節がキュッとくびれているのが特徴の、コシボソヤンマでした。この個体は雌で、 雄はこれよりもさらに細くくびれます。ここから数百mほど離れた谷戸でも足もとを低く 飛ぶコシボソヤンマを目撃したので、意外と、高い密度で生息しているのかもしれません。 少ないながら、長池公園や大栗川でも記録があり、河川の上流域から中流域までずいぶんと 広い範囲に分布するのには驚きです。晩秋とはいえ、まだまだトンボから目が離せません。 もう一つ、面白いものを紹介します。市の職員が数日前に森の中で見つけたというキノコ。 私が以前このブログで紹介したオニフスベに似ているけれど、小さいサイズのまま何日も 同じ状態・・ということで、ついでに
Nov 11, 2025


センブリのお花畑
11月7日、梶川緑地の大イチョウ周辺と梶川公園の草刈りを行いました。作業中、1年くらい お会いしていなかったあるご夫婦とバッタリ。鹿島・松が谷方面をフィールドに野鳥観察を 楽しんでおられるお二人とは、以前は草刈りや巡回の度によく鳥談義に花を咲かせたもの です。今でも、変わらず穏やかな眼差しで野鳥に目を向けている姿を見て、癒されました。 「この木(アキニレ)にはカワラヒワがよく来ますよね!」と話していたら、そのそばから “ピリリリ、ビーン”と鳴きながらカワラヒワの群れが梢に飛んできました。あまりにも タイムリーで「元気そうな○○さん(私)とカワラヒワに会えて、今日はいい日だなぁ!」と グータッチを求めてくるご主人、素敵です。皆さんとのやりとりは本当に励みになります。 日中、堀之内東山そらみの森緑地で2023年に見つかって以来、保護してきたセンブリ群落を 見に行ってきました。ちょうど花盛りで、一面にお花畑が広がっていました。今年発芽した 実生個体、開花個体とも数は明らかに増えており、生育は良好の様子。雑草はぼうぼうでは なく程良く生えている感じなので
Nov 9, 2025


なりすましサギ
11月6日、朝から姿池にダイサギがいたよと、自然館スタッフから情報提供がありました。 普段、姿池で見る大きな鳥はアオサギとハシボソガラスがほとんどなので、確かに珍しい。 午後の空き時間に行ってみると、さすがに姿池にはもう鳥影はありませんでした。しかし、 堤防を挟んだ向かいの築池の倒木上に、ダイサギが休んでいました。あ、移動したのかな? さすがの存在感で、立ち止まってスマホで写真撮影を試みる人も多数。まるで絵画のような 美しい情景に、しばらくうっとりと眺めてしまいました。そしてあることに気付きました。 こちらが朝、姿池を歩いていたというダイサギです。むむ・・築池の子と別人ではないか! 首を伸ばしているのでそもそも違う感じに見えますが、そこではありません。足にご注目。 少しわかりにくいですが、姿池にいた子は脛(すね)から跗蹠(ふしょ)の一部までの範囲が 黄白色をしているのに対して、先ほどの築池の子は足全体が黒いことが確認できたのです。 つまり、別の個体に入れ替わっていたわけです。写真に撮ってあったからこそ、気が付く ことができました。さらに、この違い
Nov 8, 2025
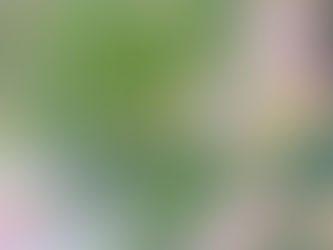

秋咲きのマンサク
11月5日、春の第一弾に続く共同企画として上柚木公園で秋の自然観察会を開催しました。 指定管理者「スポーツ&グリーン上柚木」が管理運営を行う上柚木公園は、陸上競技場を はじめとするスポーツ施設の充実した運動公園ですが、大栗川のかつての流路に沿って、 雑木林の崖線が連なるほか、園内には自然草原などが残っており、自然の質も高いはず・・ 上柚木公園の“みどり”の魅力や価値を掘り起こし、楽しんでいただこうというわけです。 約2時間半の観察会は、はじめから終わりまで盛りだくさんの内容となりました。参加者の 熱心さにはこちらも驚くほどで、次々に発見や質問が飛び出します。集合場所で待ち時間の 間に見つけられたということで、エノキの実生に止まるアカボシゴマダラの幼虫の観察から 始まったのですが、コスモス畑もじっくり見ていきたい。なぜなら、コスモスの周りに群生 する外来雑草のコセンダングサと、おなじみのコスモスがじつはとてもよく似ていることを 紹介したかったからです。そんなわけで行ったり来たりしているうちに、開始20分が経過。 いつもどうり、順調です笑。色々観察し
Nov 7, 2025
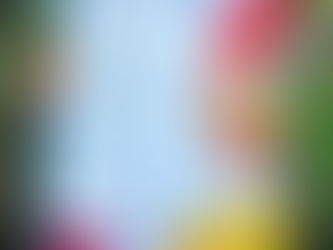

別所小学校1年生と秋の色集め
11月4日、別所小学校の元気な1年生の皆さんが、秋を探しに長池公園へやってきました。 前回、チュウゴクアミガサハゴロモ探しに夢中になった面々。今回は“色”がテーマです。 かつて、日本人は自然の中に様々な色を見出して、自由に名前を付けていました。そんな、 伝統色の中から選び抜いたオリジナルのカラーチャートを配布して、まずはお手並み拝見。 くちば色、なでしこ色、とうもろこし色・・おんなじ色の葉っぱや木の実は見つかるかな? 次は見つけたものの色を何かに例えて、今度は皆さんが色の名前を作る番です。素敵な色が たくさん生まれました。きらきら色やオーロラ色など、想像力を掻き立てる響きですよね! 綺麗な落ち葉やどんぐりを拾い集めたり、赤トンボが遊びに来たり、色探しのミッションは 里山の秋を思い思いに味わう時間でもあります。全員が最高の表情で楽しんでくれました! 授業のあとは、今月15日に開催されるフォト講座(日本自然保護協会・ソニー共催)の下見を 行いました。現在、展示室2で開催中のフォトコンテスト入賞作品展とのタイアップ企画と して毎年恒例となっているイベン
Nov 6, 2025


アプリ片手に松が谷散策
11月3日、東京都と㈱バイオームの共同プロジェクト「東京生きもの調査団」の課外活動と して、バイオームアプリを使った自然観察会が松が谷周辺で開催され、講師を務めました。 「東京生きもの調査団」は、東京都の生物多様性を守るために、東京都・専門家・都民が 一体となり、デジタル版野生生物目録「東京いきもの台帳」 を作成するプロジェクト。「いきものコレクションアプリBiome」を使い、市民科学の力を活かして東京の野生生物の 情報を収集・蓄積していくものです。都民一人ひとりが調査員・・素敵な取り組みですね! 東京いきもの調査団 課外活動~多摩丘陵編~ in 松が谷エリア - 東京いきもの調査団 都内各地から集まった参加者とともに、松が谷遊歩道さんぽみちをゆっくり歩き始めます。 生きもの好きの子どもたちも参加していて、次々に動植物を見つけては教えてくれました。 私一人だったら、つい草木や鳥、昆虫ばかりに目がいってしまう散策も、クモやヤスデ、 ナメクジ、コケ、地衣類、キノコなどなど・・生きとし生けるもの全てに目を向けます。 私も負けじと、樹名板の裏のヤモリ&カ
Nov 4, 2025


うばめがしい秋の一コマ
11月2日、メジャーリーグでの日本人選手の活躍に心を動かされた方も多いことでしょう。 私もその一人です。海の向こうの出来事に、幾多の人々が注目し、感動を分かち合う・・ スポーツの力は凄いですね!スケールこそ全く違いますが、自然体験も人々の心を動かす 素晴らしい力を持っていると思います。感動の連鎖が、少しずつ広がっていきますように。 さて、長池公園のお隣、道向かいの松木公園には長池公園には無いものが色々とあります。 その一つがウバメガシのどんぐりです。ウバメガシは南方系の樹木で、自生地は沿岸部など 潮風の当たるような環境ですが、内陸でも公園樹や生垣として植えられることがあります。 備長炭の原材料としても有名ですね。ウバメガシは花の咲いた翌年の秋に果実を付けます。 果実は確かに、帽子(※パンツとも表現される)付きの、いわゆるどんぐりそのものですが、 注目すべきはその色・かたち・大きさがバラバラで、じつに多様性に富んでいることです。 色や形の揃ったどんぐりのほうが使い勝手が良さそうではありますが、ウバメガシの場合は その不揃いさを逆手にとって、それぞれ
Nov 3, 2025


誰のお尻?
11月1日、早いものでもう11月です。毎年のことなのですが、10~12月は対応が立て込み、 うっかりすると秋の自然の見どころを逃してしまうので、季節の変化を五感で味わうための アンテナは大切にしつつ過ごしていきたいと思います。意識次第で景色も変わるものです。 この日は休みでしたが、所用でちらっと長池公園へ出向くと、パーキッズの小学4年生で 野鳥観察にのめり込んでいるKくんが家族で散策に来ていました。私も彼と同じ歳の頃には まだ見ぬ野鳥を追い求めて各地に出かけていたので、自分と重ね合わせてしまうのでした。 それにしても、第二デッキの茂みに佇むキビタキを目ざとく見つけたり、小鳥の地鳴きを 一つ一つちゃんと聴き分けていたりと、短い期間で急成長を遂げたことが伺えて感心感心! つくいけの道を一緒に歩いていたら、頭上で大きな声がしました。見上げてみると、お尻! 正体はこの子、最近渡ってきたばかりで体験ゾーンを縄張りにしているジョウビタキです。 この子は、いつも落ち着きがなく気が立っているように感じます。渡来直後だからなのか、 性格的なものなのか、もう少し時間
Nov 2, 2025


体験ゾーンの小鳥たち
10月31日、自然環境保全実習3日目は、先日のタマノカンアオイ調査の続きとマダケ林の 管理を行いました。少し時間に余裕があったので、体験ゾーンの田んぼ脇水路を利用する 小鳥たちの行動を観察しました。この場所は水浴びに訪れる小鳥の観察ポイントなのです。 水場へ降りる途中で小鳥が伝ってくる枝に、鮮やかに紅葉したエビヅルが絡んでいました。 ここに止まってくれたら秋らしくてとてもいいな・・と妄想していると、心を読まれたのか メジロがちょこんと立ち止まってくれました。背景の枝などがごちゃごちゃしているので、 写真としては今ひとつかもしれませんが、季節感のあるシーンを記録に残せて大満足です。 田んぼの周囲には、冬鳥のジョウビタキと夏鳥のキビタキ、留鳥のコゲラなどがいました。 先日のカイツブリはすでに姿が見えなくなっていて、築池には代わりにマガモがいました。 これらのほかに、漂鳥のアオジ、クロジ、シメ、ビンズイなども先日から確認しています。冬が近づき、鳥たちも存在感を増してきました。ぜひ双眼鏡を片手にお出かけ下さいね!
Nov 2, 2025


癒しのエナガ
10月30日、自然環境保全実習2日目は雑木林トレイルの一角にあるタマノカンアオイ群落の 個体数調査や、センサーカメラの設置などを行いました。全部で162個体をマーキングし、 個体ごとに生育状況や展開している葉の枚数などを丁寧に調べて、モニタリングしました。 頭上ではエナガの群れが賑やかに飛び回っており、作業の疲れを吹き飛ばしてくれました。 なぜかシマエナガのほうが一般の認知度が高い昨今ですが、本州に生息するエナガだって 可愛さでは負けていません。シマエナガと違って目の上に太い黒のラインが入っています。 群れの中に一羽、こんな子が混ざっていました。エナガの特徴ともいえるあの長い尾羽が 見当たりません。尾羽が無いと真ん丸でまるで別の小鳥のようです。秋は換羽の季節なので おそらく尾羽が生え変わる途中の姿ではないでしょうか。マシュマロみたいで癒されます! ヤマガラやガビチョウも作業の様子を覗きに来てくれました。いや、むしろ私たちが彼らの 生息域に踏み込んでいたのでしょう。植物はヤクシソウ、ノコンギク、ノハラアザミです。 ナラ枯れ木を伐採した跡地を中心に、
Nov 2, 2025


チュウゴクアミガサハゴロモの捕食者
10月29日、専門学校東京テクニカルカレッジ2年の自然環境保全実習がスタートしました。 初日は終日、自然館での座学です。話すのも聞くのも大変ですが、フィールドでの実習に 先駆けて、野外活動での心得や作業上のリスクマネジメントを学ぶことはとても重要です。 特に危険生物や野外での事故の項目では、自身のエピソードトークが役立ちます。説得力の ある注意喚起ができるからです。学生たちもきっと危機意識を持つことができたはずです。 ところで、先日の道草くらぶ活動のときに、ながいけの道で拾ったこちらの羽。落とし主の 正体はわかるでしょうか?羽軸を挟んだ片側がブルー、片側がブラックの二色の尾羽です。 正解はこちら。シジュウカラです。青い鳥を想像された方も多いと思いますが、意外にも、 白黒の小鳥の羽なのでした。写真で見ると、確かに翼や尾羽が青灰色味がかっていますね! そしてこの写真は授業の休憩時間に自然館中庭で撮影したものですが、よく見ると、アレを 咥えています。そう、昨今話題のチュウゴクアミガサハゴロモです。こんなにあちこちに 数多く生息しているのだから、小鳥が食
Nov 2, 2025


みちくさもみじ
10月28日、園内の草花に名札を設置しつつ植物を学ぶ「道草くらぶ」の活動を行いました。 愉快で陽気な面々と、この日も珍道中が始まりました。植物の名前は必ず聞き間違えるし、 何回も同じ質問を繰り出す皆さん、期待を裏切りません笑。でも、楽しいのが一番ですね! 雑草にも目を向けてもらいたいという思いから、今回は地味でありふれた草花にも名札を 付けてみました。そんな中、ひっつき虫の王道の一つであるヒカゲイノコヅチに目を奪われ ました。見て下さい!この美しい草紅葉!これまでも、葉の色付く草花をたびたび紹介して きましたが、思いもよらない雑草が紅葉しているのを見つけたときの感動はまた格別です。 ながいけの道など、園内の各所に群生しているカラスノゴマも葉が赤く色付いていました。 真っ赤も良いですが、1枚の葉が緑から赤へとグラデーションになっているのも綺麗です。 この時期、ほとんど花の目立たないカタクリ観察路では、白いブラシのような姿が印象的な サラシナショウマの花が咲いていました。思わず触ってみたくなる可愛らしい花ですよね! 散策中に出会った植物と昆虫の一部で
Nov 1, 2025


秋色彩々
10月27日、長池公園では草木の葉が色付き、一年でもっとも彩り豊かな季節の到来です。 駐車場から自然館まで、普段なら素通りしてしまう植栽されたガマズミも、ほらこの通り。 ドキッとするような美しさです。黄葉したアカシデの落ち葉に私も影で埋もれてみました。 この日、午前中は「いきものがかり植物班」の活動で自然館周辺の手入れが行われました。 メンバーのお一人、Tさんが引っ越しされるとのことで、これが最後の参加となりました。 Tさんには、長きにわたり、お世話になってきました。中庭や自然館周りの保護植物などを 手厚く見守り、丹念に育ててきて下さりました。そしてこのブログも読んで下さっていて、 動植物の生きざまについて、参考になる情報を惜しみなく教えて下さり、語り合いました。 最近は私が忙しくて、なかなかゆっくりお話できなかったことが悔やまれます。この日も、 樹木移植の現場立ち合いに出ていてお会いできませんでした。この場を借りてこれまでの 感謝の意をお伝えします。たくさんご尽力いただきありがとうございました。新生活でも Tさんらしく、自然観察を続けていかれる
Nov 1, 2025
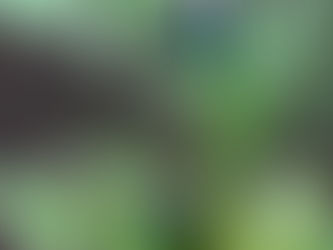

メリケントビハムシ
10月26日、先週の千葉市の調査では、巨大なオニフスベとの遭遇に気持ちを持っていかれて すっかり忘れるところでしたが、もう一つ個人的に嬉しい出会いがあったので紹介します。 それがこの美しい外来昆虫、メリケントビハムシです。2020年に国内では初めて茨城県で 発見され、その後関東地方のほぼ全域に定着していることが明らかとなり、2023年に和名と ともに発表されたばかりの甲虫です。近年、各地で話題になっていたので見ておきたかった 昆虫の一つでした。じつは近所でもすでに観察されているのですが、私はこれがお初です。 似たようなハムシがいるのですが、本種の食草であるイヌビユを美味しそうに食べている 様子を観察したこと、撮影後に指で触れようとするやいなや“ピュッ”とどこかへ跳んで 逃げたことから、確信が持てました。写真で見るよりもずっと青味が強く、前胸の赤色との コントラストがかなり目を引きました。これから、この辺りでも増えてくるでしょうか? アメリカ原産のメリケントビハムシよりも、一足先に市民権を得た(?)中国原産の彼らは、 今年はもうどこへ行っても必ずと
Oct 31, 2025


あめでもともと
10月25日、朝から雨で観察会が一件中止になりました。午前中のパークキッズレンジャーの 活動と、午後から市内の緑地で出張講師を務めることになっていた「里山レンジャーズ」の 活動は、雨にも負けず、どちらも決行に。私は日頃から“雨だからこその愉しみ”を探求 しているので、荒天など危険が伴う場合を除き、悪天候のフィールドワークも大好きです。 そのことをよくわかっているパーキッズの子どもたち+親御さんが大集合してくれました! パーキッズの活動は園内に設置してあったセンサーカメラの回収と解析です。早速、霧雨の 園内へ繰り出します。築池の堤防では、チカラシバにたくさんの水滴が付いて、とっても 幻想的な光景が広がっていました。近付いてみると、ウスバキトンボが一休みしています! そうか、雨の日はこういう場所でじっと翅を休めていたのですね。そっと指を近付けて・・ 手乗りウスバキトンボです。乗るというより、ぶらさがっているほうが落ち着くようです。 子どもたちの指を伝ってリレーしていきます。こんなこと、雨の日じゃないとできません! もう1種類、翅を休めている昆虫がいま
Oct 31, 2025


夏の名残りと冬の使者
10月24日、堀之内沖ノ谷戸公園の参道沿いの草刈りを実施しました。ずっと後回しにして しまっていた、展望台下のクチナシグサ群落も選択的草刈りを行いました。ススキは少し 塊で残して虫たちの退避場所を確保したので、生きものの拠り所になるかもしれません。 作業車両で堀之内東山はぐくみの森緑地を通りがかった際、車の目の前に小鳥が飛び出して きました。ロープ柵に止まった姿を確認するとジョウビタキでした。この辺りでは冬鳥の ジョウビタキですが、先週くらいから続々と渡来情報が届き、私自身も確認していました。 車を降りて証拠写真を撮っていると、今度は別の雌と雄3羽が次々に飛来し、小さな群れで 動いていることに気付きました。ジョウビタキは渡来して間もなく単独で縄張りを確保する 習性があるので、複数個体が一緒にいるのは珍しい光景です。おそらくまだ渡りの途中で、 これからさらに南下する個体群が立ち寄っていたのだと思われます。秋らしい光景でした。 地上に葉を広げているクチナシグサに注意を払いながら草を刈り進んでいる時に、ふと横の クヌギの木に目を向けると、なんとスズメバ
Oct 30, 2025


イシミカワの彩りと長池自然学校!?
10月23日、自然館中庭では鮮やかな瑠璃色をしたイシミカワの果実が見頃を迎えています。 瑠璃色の部分は花被が実を包み込んだもので、はじめは淡いクリーム色をしていますが、 やがて桃色~赤紫色に色付き、そこから青味が増していきます。一つの果序に様々な段階の 果実が見られるのでとてもカラフルです。先日の千葉出張でもイシミカワに出会いました。 果実の美しさもさることながら、この植物は“かたち”も魅力的です。茎を抱き込むように 付いた真ん丸の葉っぱ(托葉)と、長い柄のある三角形の葉っぱ。そのどちらも、一つの茎に 見ることができます。たとえ果実が無くても、“丸”と“三角”の葉っぱが同居していれば イシミカワと判別できるでしょう。また、他の植物によじ登って伸長する習性があり、茎に 斜め下向きの鋭いトゲがたくさんあるのも特徴的です。観察の際にはトゲにご注意下さい! 群落の中に、果皮が失われて中の実が剥き出しになっている個体を見つけました。意外な ことに、中の実は光沢のあるブラックでした。このままでも十分目立ちそうなものなのに! さて、この日は長池公園に多くの子ど
Oct 29, 2025


念願のオニフスベ
10月22日、企業案件で千葉県某所の都市開発予定地へ出張してきました。関係者の皆さんと 現場を歩いての調査観察はこれが3回目でしたが、この日もまた良い出会いがありました。 調査地に隣接する谷へ足を踏み入れた直後、遠くにバレーボールのような塊が見えました。 あれはもしかして!・・近付いてみるとやはりキノコでした。大きなものは直径30cmほど! ハラタケ科のオニフスベという種類で、日本特産にして最大級の“お化けキノコ”です。 今回見つかった個体の多くは、すでに白い外皮が消失して褐色の内皮が剥き出しになって いましたが、この内皮の内側にはぎっしりとほこり状の胞子塊が詰まっていました。触った 感触はパンのように柔らかく、ゴムボールのように軽くて転がすとコロコロ止まりません。 小さい頃に眺めていたキノコ図鑑に載っていて、そのビジュアルに衝撃を受けたのをよく 覚えています。ずっと見てみたいと思っていたのですが、なかなか縁がありませんでした。 そんなわけで、見つけた瞬間から子どものように興奮しっぱなし。林縁に点在して生える オニフスベをひとしきり観察したあとは
Oct 28, 2025


モミジルコウと長池小学校4年生クズとり
10月21日、調査の仕事で通りがかった空き地に、鮮やかな朱色の花が群生していました。 ヒルガオ科のモミジルコウ(ハゴロモルコウソウ)という植物です。栽培品の逸出でしょう。 マルバルコウとルコウソウの交配種で、葉の切れ込みは両者の中間的。モミジのような形を していることからその名が付けられました。最近はどこでも見かけるマルバルコウと違い、 モミジルコウを目にする機会はあまり多くありません。ちょっと嬉しい出会いなのでした。 この日の調査は、熱心な市の職員お二人と一緒にいくつかの緑地を廻りました。思いがけず コシオガマやカエデドコロなどのやや希少な種類も記録できて、上々の成果を挙げました。 写真は順に、コシオガマ、シュロソウ、イヌショウマ、タチツボスミレ、ボタンクサギ、 ウシハコベ、ヤクシソウ、ヒメセンナリホオズキ、アメリカアサガオ、カエデドコロ、 ノブドウ、イヌアワです。※季節外れのタチツボスミレは水辺で返り咲きしていたもの。 一方、午前中は長池小学校4年生による体験プログラム第2回(第1回は姿池清掃)のクズとり ミッションが実施されました。小学校の
Oct 26, 2025


マルバツユクサの繁栄と公開座談会
10月20日、午前中は港区青山の「地球環境パートナーシッププラザ」へ出張してきました。 関東EPOと環境再生保全機構が主催する、都市の環境保全活動に関する公開座談会に登壇 するためです。途中、電車が運休になるアクシデントに見舞われてどうなることかと・・ 朝一番、京王堀之内駅前の歩道沿いにマルバツユクサがたくさんあるのが目に入りました。 堀之内周辺では、主に大栗川よりも北側に広く見られる雑草で、造成土や畑の堆肥に種子が 混入して持ち込まれ、定着したとみられます。旺盛な繁殖力によってみるみるうちに分布を 広げてきました。もともとは南方系の雑草なので国内外来種とされていますが、国内だけで なく、東南アジア産のヤシ殻堆肥など、大陸から渡来した系統も多いことが予想されます。 地中に閉鎖花を付けて自家結実することもあって、分布の広がり方が尋常ではありません。 座談会を無事に終え、青山の街角で最初に出迎えてくれたのもこのマルバツユクサでした。 2つずつ並んだ花が愛らしく、足を止めてカメラを向けてみました。丸葉も可愛いですね! こちらが登壇した「都市部における“
Oct 25, 2025
bottom of page
