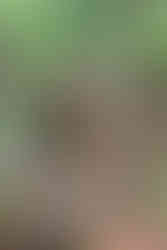秋深まる
- ひとまちみどり由木 指定管理者
- Oct 20, 2025
- 2 min read
10月16日、長池公園では早くもジョウビタキの雄が初認されました。近年は国内でも多数の
ペアが繁殖しており、もしかすると国内を南下する途中で立ち寄った個体かもしれません。
夏鳥のキビタキもまだいますし、本格的に姿を見るようになるのはもう少し先でしょうか。
この日は、調査の仕事で市内3ヶ所の民有緑地を廻ってきました。最初に訪れた緑地は隣接
して栗畑が広がっており、なんとも秋らしい光景に出会えました。クリは、秋の味覚として
日本を代表する伝統果樹の一つですが、そのルーツは古く、縄文時代にはすでに利用されて
いたことが知られています。植物としてのクリの起源は驚くほど太古までさかのぼります。
6000万年以上も昔、恐竜たちが闊歩した白亜紀後期にクリの祖先が生育していたのだとか。
クリが歩んできた途方もない歳月と、人々との関わりの歴史に思いを馳せてしまいますね。
栗畑の足もとにはハマハナヤスリ、コハナヤスリ、コヒロハハナヤスリなどハナヤスリ類が
一面に混生していました。適度な湿り気があり、程良く草刈りされる芝草地が彼らにとって
好条件のようです。雨の雫がキラリと輝いたヌカキビの佇まいにも、思わず足を止めます。
草むらを歩けば、様々な野菊と出会います。ユウガギク、カントウヨメナ、シラヤマギク。
その他の草花は、写真のみご紹介します。ツリガネニンジン、シロバナツリガネニンジン、
シロバナミゾソバ、ノハラアザミ、ナンバンギセル、アキノキリンソウ、クチナシグサ、
センブリ、ニシキソウ、チョウセンガリヤス、ハイヌメリ、アキネジバナ、以上は在来種。
13枚目以降はアメリカキンゴジカ、ヒメマツバボタン、アメリカアサガオで外来植物です。
まだまだ昆虫シーズンも続いています。クビキリギス、オオホシカメムシ、ミヤマアカネ。
対象地3ヶ所の調査を終えるとすっかり日が傾いていました。事務所へ戻り、オンラインで
大学院生のヒアリングに受け答えつつ、秋の情緒溢れる一日の余韻に浸っていたのでした。