top of page


落ち葉かき二本立て
1月26日、午前中は別所小学校おおぞら学級の皆さんと雑木林の落ち葉かき、午後は里山保全隊でカタクリ生育地の 草刈りと落ち葉かきを行いました。カタクリをはじめ、春に開花する植物の発芽を促すための大切な里山仕事です。 よく「落ち葉かき」と「落ち葉はき」が混同されていますが、前者は雑木林の土の上に降り積もった落ち葉を熊手で “かき集め”て林床植物の発芽を促し、成長を助ける役割があるのに対し、後者は園路などに溜まった落ち葉を箒で “はき寄せ”て滑りにくく、美しい景観を保つ目的があります。どちらも、集めた落ち葉を活用して腐葉土を作ると いう点では共通していますが、極端にいえば、落ち葉かきは自然のため、落ち葉はきは人のための作業なわけです。 落ち葉をかいて地表の土が露わになると、黄緑色の新芽がいくつも顔を出していることに気が付きました。近付いて よく見ると、キツネノカミソリの若葉でした。なんと、落ち葉の下ですでに発芽していたとは予想外で驚きました。 ニワトコの新芽がぷっくらふくらみ、その下では葉痕がボーッとこっちを見ています。「鏡を見ているようだわ~」と..
11 hours ago


マツムラグンバイに軍配!
1月24日、パークキッズレンジャーの定例活動で、里山で冬越しする生きもの調べと展示づくりに取り組みました。 観察の前に“予想タイム”を設けて、どんな生きものがどんな姿(大人?子ども?卵?蛹?)でどんな場所にいるのか みんなの記憶を手がかりにしながら色々想像してみました。私の思惑どおり(?)、「樹皮の裏側」というアイディアが 出てきたところで、この日は樹皮裏を中心に生きものを調べて、体験できる展示を作ろうということになりました。 ブログでもたびたび取り上げているように、ここ数年は樹皮裏で冬越しする生きものに注目してきました。確認した 生きものをリストアップしておいたので、観察の前に配布します。「このリストに載っていない生きものを見つけたら 大発見だよ!」とその気にさせて、いざ出発!最初はスギの樹皮裏です。カメムシ類が見つかることが多いので期待 していると、間もなくYくんが小さなカメムシのような昆虫を2匹見つけてくれました。その場では名前がわからず。 つまり、いきなりリストに載せていない種類だったのです。ほぼ同じ時に近くの朽木をほじくっていたSくんた
1 day ago


ミツバウツギのポートレート
1月23日、八王子市斜面緑地保全委員会に出席しました。私は最大任期の8年を迎えるため、最後の委員会でした。 この8年間、委員としての務めを少しは果たせたのではないかと思っています。色々と意見をさせていただきながら、 評価基準の見直しや新しい制度の立ち上げ、ボランティア体制の構築、現地調査の実施など様々な発展的展開へと、 繋げることができました。また、私自身もそれまでは市内のみどりに関しては、公有地(公園緑地や保全緑地)のこと しか認識がなかったのですが、民有地(斜面緑地)の有する自然的価値を実感し、その保全というところにまで自らの 視野を広げることができました。委員ではなくなりますが、市内に40ヶ所以上も指定されている全ての斜面緑地を、 3年かけてこの足で実際に歩き、調べ上げた身として、今後も関わり続けて責務を果たしていきたいと考えています。 真面目な話はこれくらいにして、長池公園の水辺や雑木林で数多く見られるミツバウツギの冬の姿をご紹介します。 葉痕が可愛い子どもの顔に見えて、ついクスッと笑ってしまうのは私だけでしょうか。落葉後の冬姿がよく似て
2 days ago


カラスザンショウのポートレート
1月20日、施設点検で大塚・東中野方面の公園緑地を廻ってきました。年末大掃除の名残りでしょうか、あちこちに 衣服やシーツの投棄があって回収しました。以前、公園に捨てられたシーツの中から何匹ものヤモリが出てきたのを 思い出します。生きものにとっては“棚から牡丹餅”かもしれませんが、私たちには物騒なモノでしかありません。 話は変わりますが、長池公園の雑木林では、カラスザンショウの実生木が増えています。数年続いたナラ枯れにより 倒木したり伐採を行ったりした箇所を中心として、雑木林内の各所に“ギャップ”といわれる空間が生じています。 それまで幅を利かせていた大きな木がなくなり、地表まで直接光が差すような大きな隙間ができるのです。こうした 環境では一気に下草が勢力を増してくるわけですが、それと同時に、成長が早くパイオニア的性質を持った落葉樹の 赤ちゃんがニョキニョキと育ってきます。実を食べる小鳥が運んでくるサンショウの仲間やクサギ、クマノミズキ、 ヌルデ、ハリギリなどです。中でも、あっという間に大きくなって実を付けるまでに成長したカラスザンショウは、...
3 days ago


冬の過ごし方
1月19日、南エントランスゾーンのさくらトイレ向かい、桜並木の周りで冬越しするフデリンドウを観察しました。 落ち葉を掻き分けると、ちゃんとフデリンドウらしい形で生えているのが次々に見つかりました。何だか今にも花が 咲きそうな気がしてしまいますが、開花は春。この状態のままあと3ヶ月くらい過ごします。もともと植物体が小さい ので、ロゼット状になる必要はないのかもしれません。秋に芽生えて冬を乗り越え、春に開花する、そうした生態を 持つ植物を越年草といいます。自ら苦難に飛び込んでいくようで変わっているなぁ・・でもよく考えたら、そこいら じゅうに生えているハルジオンやオオイヌノフグリ、ハハコグサなども同様の生活史であることに気が付きました。 外来雑草や史前帰化植物は、原産国の気候に合わせた生活史を備えているはずなので、母国では冬も雨が多いなど、 越冬に適した条件だったのかもしれません。“日本の冬は寒いし乾燥するし大変だなぁ”と愚痴が聴こえてきそう。 園内を歩いていると、目の前にウグイスが現れました。“チャッチャッ”という地鳴きはよく聴きますが、その姿を..
6 days ago


イラガの繭と泥だらけのパーキッズ(投稿1111件目)
1月18日、早いもので、この投稿で1111件目のようです。次のゾロ目までは果てしない長旅になりそうですが笑。 先日、自然館前の冬芽と葉痕を紹介しましたが、もう一つ面白い観察ネタを取り上げます。写真のイラガの繭です。 ウッドデッキに張り出したオオバヤシャブシの枝先に付いています。鳥の卵のようにも見えますが、硬い殻を持った 繭で、不思議な模様が入っているのが特徴です。この模様は、一つとして全く同じパターンは無いといいますから、 見比べてみるのも面白いです。飲料販売機近くの水鉢のヤナギの枝にも、繭が2つ付いているので探してみましょう! 繭の中にはイラガの前蛹が入っていて、上部がパカッとフタのように開いて初夏に羽化します。しかしながら、時々 イラガセイボウという青いハチに寄生されているものがあり、イラガではなくハチが出てくる場合もあるようです。 パカッとフタが開いて羽化が完了したあとの繭殻のことを、“スズメノショウベンタゴ”と呼ぶ地方があるそうな。 色々知ると、探すだけでなく、その後の経過もしっかり観察してみようという気になってくるから不思議ですよね。.
Jan 19


ゴマギのコックさん
1月17日、今年初めてのサタデーパークボランティア活動が行われました。内容は第一デッキ湿地の枯草刈り取り。 翌18日のパークキッズレンジャー活動で予定しているカエルの産卵池掘り込みに先駆けて、作業が進められました。 ところで、冬の里山の愉しみといえば、「冬芽と葉痕」です。木々が葉を落とし、硬い冬芽の状態で冬を越す様子は、 樹種や個体によって様々な個性に溢れているので、何回観察しても飽きません。ウォーミングアップとしてこちらの 冬芽と葉痕を観察しました。正体は、長池公園自然館の入口脇に植栽されたゴマギです。ゴマそっくりの香りがある 葉は注目の的ですが、殺風景な冬姿をまじまじと見ることはあまりないのではないでしょうか。冬芽は、2対の芽鱗に 包まれています。外側の2枚は早く剥がれ落ちてしまいます。その下に葉を落とした痕の葉痕(維管束痕)があります。 葉痕は断面の維管束痕が顔のパーツのように配置されています。皆さんにはいったい何の顔に見えますでしょうか? 「ふゆめがっしょうだん(福音館書店)」や「冬芽ハンドブック(文一総合出版)」をはじめ、冬芽や葉痕を取
Jan 19


雑木林で嬉しい拾いもの
1月15日、園路沿いの枯れ木の伐採作業により、つくいけの道が一時通行禁止となりご迷惑をおかけしております。 安全第一でもちろん私たち管理者も通行できないので、雑木林トレイルを通って里山トイレを開錠しに行きました。 黙々と歩く私の目の前にヒラリと舞い降りたのはキセキレイです。なぜかずんずんこちらへ向かって歩いてきます。 近すぎてピントが合わなくなる寸前で、なんとか撮れました。可愛い小鳥を可愛く撮れた瞬間の喜びは格別ですね。 任務を終えた帰り道、炭焼き小屋裏手の階段で鳥の羽毛を拾いました。少し離れたところにもう1枚。何でしょうか? 1枚目はフクロウの体羽、2枚目はアオゲラの上尾筒のようです。最近、日没後にスタッフが相次いでフクロウを確認 して話題になっていたこともあって、証拠として特に嬉しい発見となりました。受付の羽展示に加えておきますね! いつもなら平坦なつくいけの道を選んでしまいますが、たまには遠回りして雑木林を通ると良いことがあるかも!?
Jan 17


ヒメシャラの重ね着
1月13日、近隣のバイオマスエコセンターから、体験ゾーンで活用する堆肥を譲り受けてきました。昨年も田んぼに 施用し、収量が増加したそうです。梅園右手の広場に仮置きされた軽トラ8杯分の堆肥は少し臭いますが悪しからず。 さて、最近は動くものばかり観察していたので、この日は寒い冬を静かに耐え忍ぶものたちに目を向けてみました。 最初に注目したのは自然館中庭のヒメシャラの木。どんな冬芽をしていたかなと、枝先を見てみると、とても美しい 模様の冬芽が並んでいました。模様を形作っているのは芽鱗といい、大事な新芽を守るカプセルのような構造です。 5~6枚の芽鱗が重なり合って配列しているのがヒメシャラの特徴です。近縁種のナツツバキ(シャラノキ)は、芽鱗が 2枚しかないことで区別できます。よく言われる覚え方は“ヒメは厚着でナツは薄着”という語呂合わせ。うまい~! ヒメシャラの根元の落ち葉を掻き分けると、早くもフクジュソウの芽が顔を出していました。タケノコみたいです! 堀之内寺沢里山公園の陽だまりではすでにフクジュソウが咲き始めているそうなので、こちらももうじきでしょう
Jan 17


ゲゲゲの・・・
1月6日、山開きまでの間、まだしばらくは緑地作業がお休みなので、事務仕事など細々とした作業を進めています。 この日は、擁壁の安全点検で各公園を廻ったり、掲示物を貼り替えたりと、公園管理者らしい業務に奔走しました。 そんな作業の合間に癒してくれたのはルリビタキです。今年も美しい雄に出会えました。最初の換羽で大人の羽衣に ならず、3年くらいかかってやっと背面全体が青くなるという、小鳥では珍しい生態を持っていることから、必然的に 見かけるのは茶色っぽい個体ばかりになります。その珍しさも相まって、雄の中でも特に青い子は人気があります。 念のため、詳しい場所は書かないでおきますが、ここでは青い子とは別にもう1個体、茶色いタイプの子が隣り合って 縄張りを作っています。両者のテリトリーは互いに重なっていませんが、同所的に、ジョウビタキとモズも縄張りを 構えてパトロールしているので三つ巴状態になっています。良い採餌場を巡って、今後は争いが絶えなさそうです。 ちなみに、タイトルの「ゲゲゲ」は鬼太郎ではなく、ルリビタキの地鳴きです。この声を覚えておくと便利ですよ!.
Jan 8


おしゃれなジョウビタキ
1月5日、私にとってはこの日が仕事始めとなりました。初日は当番で松が谷方面の巡回清掃を行いました。休み中に どっさりとゴミが捨てられていたり、トイレットペーパーの予備が空になっていたりしましたが、平和なほうです。 大きな異常がなくてほっとしました。常連の皆さんにも、鳥たちにも新年のご挨拶をしつつ、ゆっくり廻りました。 巡回のついでに堀之内方面の公園に立ち寄ったのですが、足もとへやってきたジョウビタキの雌を見て驚きました。 なんと雌なのに、胸からお腹まで鮮やかなオレンジ色ではないですか!ふつう、雌は腰と尾羽以外は茶色いのです。 まさかの珍種か?と思いましたが、声や行動はジョウビタキそのもの。海外のジョウビタキ属も調べてみましたが、 やはり種とてはジョウビタキで良いようです。噂によると、ごく稀に腹面が鮮やかなオレンジ色の胸をした雌が観察 されるそうで、web上でも似たような個体の画像がヒットしました。褐色のジョビコさんに見慣れた目からすると、 結構違和感があるので、最近かなり増えてきている“AI画像”を疑われてしまいそうですが、もちろん天然ですよ!.
Jan 8


年末のご挨拶(2025年)
12月31日、2025年が穏やかに幕を閉じようとしています。今年も公園利用者の皆さま、ブログ読者の皆さまには 大変お世話になりました。心より感謝致します。明日からも変わらず歩んでまいりますので宜しくお願い致します。 先週、11月に松が谷方面で発見したニシオジロビタキとの再会を果たすことができました。影響を考慮して、詳しい 場所については控えさせていただきますが、可愛らしい姿を皆さんにも見ていただきたいので、写真を掲載します。 最初に見つけたときよりも近くまで降りてきてくれました。私にとって嬉しいクリスマスプレゼントになりました。 ところで、来年の干支は午(うま)ということで、馬の尻尾に因んだ動植物を一つずつご紹介します。1枚目はその名も ウマノオバチです。2021年春に、念願叶って栗林で出会うことができました。シロスジカミキリの幼虫に寄生する 寄生バチで、名前の由来になったメスの長い産卵管が特徴です。尻尾のような産卵管はなんと体長の6倍もあります! 2枚目は身近なシダ植物の一つ、トクサです。トクサはつくしんぼのような胞子嚢穂が、茎の先端に付いてい
Dec 31, 2025


ジュウガツザクラと自然観察会のお知らせ
12月30日、今年も残すところあと一日となりました。生きものたちは冬越しの準備、私たちは年越しの準備です。 お墓参りで市外の山里にあるお寺に訪れると、冬桜の一種、ジュウガツザクラが綺麗に咲いていました。10月頃から 咲き始めることに由来していますが、実際には年明けまで華やかに咲き続けます。二季咲きなので春にも咲きます。 マメザクラとエドヒガンの交配で生まれた園芸種で、小ぶりの花は花びらが細く、半八重咲きになるのが典型です。 集落を望む丘の上で、モノトーンの冬景色に彩りを添えていました。ちなみに多摩丘陵にも時々植栽されています。 話は変わりますが、夏の猛暑の影響などもあって、しばらく開催できていなかった「長池公園 季節の自然観察会」を 久しぶりに企画しました。すっかり間が空いてしまい、申し訳ありません。冬越しする動植物などを観察しながら、 ゆっくり歩きたいと思います。また、散策のあとはブログ投稿1000回を記念(すでに1100日目前ですが・・)して フリートークも考えていますので、読者の皆さんはぜひふるってご参加下さい!申し込み開始は1月5日9時~
Dec 31, 2025


サインのフィールドサイン
12月28日、長池公園自然館は年内の開館最終日を迎えました。今年も多くの方にご利用いただき、感謝致します。 来年も引き続き、地域の憩いの場として、また、学びの拠点として、賑わいと安らぎの空間を提供してまいります。 なお、自然館は12/29~1/3まで休館となりますが、公園内はいつもどおりご利用いただけますのでご安心下さい。 ところで、道草くらぶの皆さんと園内各所に草名ラベルを設置していますが、今シーズンは道ばたの雑草に注目して もらうべく、足もとの低い位置にもいくつか名札を刺していました。それらのうちの一つが写真のようなボロボロの 状態で発見されました。まるで弾丸の痕跡のような穴がいくつも見受けられます。犯人はあの子に違いありません。 あの子とは、ホンドタヌキのことです。「ちょうどいい高さに、ちょうどいい嚙み心地のモノがあるじゃん!」という タヌキたちの心の声が聴こえてくるようです。そういえば、前にも、体験ゾーンのキランソウのラベルが穴だらけに なっていたり、九兵衛坂公園の階段沿いに設置した草名ラベルが全てかじられていたりしたことがありましたっけ
Dec 30, 2025


パーキッズ活動納めとタテジマカミキリ
12月26日、午前中は年内最後の緑地作業で、乳母ヶ谷公園の落ち葉清掃を行いました。回収した落ち葉の総量は、 なんと460kg!雨のあとで水分を含んでいたこともあり、かなりのボリュームとなりました。年明けまでしばらく 緑地作業はお休みです。作業チームの皆さん、1年間お疲れさまでした。そして、午後は同じく年内最後の実施となる パークキッズレンジャー活動です。落ち葉の裏で冬を越すチョウの幼虫調査と、雑木林の落ち葉かきを行いました。 落ち葉プールで盛り上がったあと、自然観察納めもしておきたいと思い立って、藪を漕ぎ、急斜面を上がりました。 ヒノキの木陰にひょろっと伸びたハリギリの幼木。昨年はここにタテジマカミキリが張り付いて越冬していました。 今年はどうかと覗いてみると・・いました!大人の身長よりも高いところなので観察するのが大変でしたが、全員で 冬越しするタテジマカミキリを拝むことができ、大満足です。昨年の記事はこちらです。→ 立春のタテジマカミキリ ヒノキの樹皮下では、AくんとYくんが複数のトゲヤドリカニムシを発見。越冬中のクロウリハムシやヤニサシガメ
Dec 29, 2025


手乗りシジミ
12月24日、朝から雨模様でしたが、午前中は傘を差して、東京都立大学プレミアムカレッジのフィールドワークで 長池公園をご案内しました。足もとが悪く歩くのも大変なほどでしたが、とても意欲的な皆さんに助けられました。 午後からは四半期に一度の監査がありました。忙しくて写真を撮っていなかったので、先週の話題をご紹介します。 19日の午後、縁あって、八王子市越野にある帝京大学中学校・高等学校の敷地内に残る雑木林の調査を行いました。 1995年に開学した中高一貫校ですが、これまで30年以上、敷地内の自然について本格的な調査は行われておらず、 最近ではナラ枯れによる危険性などもあり、学内外で活用されることはほとんどなくなっているそうです。折しも、 建設前に実施された自然環境調査(アセス)の資料を最近入手できたため、当時と今との環境の変化や動植物の所在に 注目しつつ、まずは現状を把握するための予備調査として、教員と有志学生の協力のもと、敷地内を散策しました。 雑木林は確かに樹木の高木化やナラ枯れの被害、竹林の拡大などが目立ちましたが、業者によって間伐や下草刈り
Dec 28, 2025


いつでもどこでもジョウビタキ
12月23日、午前中は長池小学校つばさ学級の落ち葉かき対応、夕方から楢原小学校へ出張して打ち合わせでした。 この日が今年最後の教育機関対応です。2025年4月~12月までに行った教育機関への支援件数を集計してみると、 計62件、28施設、延べ2662人にも上りました。“ながいけ自然学校”と呼んでもいいほど、よく対応しました。 この日は行く先々でジョウビタキに出会いました。こちらは、楢原小学校近くの河原にいたジョウビタキの雄です。 可愛い顔で私にガンを飛ばしているように見えます。じつは舌打ちする感じで地鳴きを真似してみたら、ずんずんと 近付いてきたところなのです。冬は単独で縄張りを作ってパトロールに余念がない彼らのことですから、きっと私を 侵入者と思って様子を伺いに来たのでしょう。ルリビタキの地鳴きも真似できるようになりたい今日この頃です・・ 朝は、長池公園の築池のほとりで雌を見かけました。売れ残っていたガマズミの実に、ようやくちらほらと来訪者が 現れるようになりました。他に食べ頃の実が無くなって急に注目されるようになったのか、それとも、人間の眼で
Dec 27, 2025
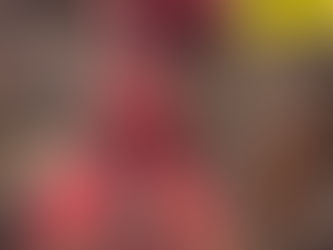

展示室1に新しい仲間
12月22日、所用で高尾の森自然学校を訪問しました。冬枯れの草原ではモズやホオジロが見え隠れしていました。 モノトーンの枯野を眺めていると、ひときわ目立つ真っ赤な植物に気が付きました。気になると正体を確かめずには いられません。草や灌木を掻き分けて見てみると、ミツバアケビの紅葉でした。アケビやミツバアケビは黄褐色とか 紫褐色に色付くイメージがあり、これほど鮮やかなものは初めて見ました。今シーズンは、木々の紅葉も草の紅葉も 当たり年なので、普段はあまり美しく紅葉しない種類の植物がいつもとは違う表情を見せてくれることがあります。 所変わってこちらは長池公園自然館展示室1の常設コーナー。大学の先生と学生さんが集まって何だか賑やかですね。 骨格や透明骨格標本を手掛けて下さっているヤマザキ動物看護大学の面々です。新しい展示が追加された模様です! 今回、新たに仲間入りした標本たちです。修復作業を終えて戻ってきたホンドタヌキの骨格、ニホンイタチの骨格、 そしてアブラコウモリの透明骨格標本です。里山の野生動物は、全身が毛で覆われていることもあって、どれもよく..
Dec 27, 2025


落ち葉清掃の癒し
12月19日、大塚にある竜ヶ峰公園とふきつけ公園の落ち葉清掃を実施しました。どちらも小さな公園ですが、特に 竜ヶ峰公園は山側から流れてくる落ち葉がてんこ盛り状態。回収した落ち葉の総量は、およそ250kgに達しました。 そんなハードワークを癒してくれるのが、時折、姿を見せてくれる小鳥たちです。「ニーニー」と鳴きながら行動して いるのはヤマガラ。「ゲゲッ」と小声で呟きながら近付いてくるのはルリビタキです。鳥見歴も30年くらいになると ちょっとした小鳥のささやきでも、どこにどんな種類が何羽くらいいるか、などの情報が瞬時に頭に入ってきます。 現場の作業に集中していても、つまり、見ようとして意識をしなくても、五感でバードウォッチングできるのです。 大好きなエナガの群れも現れました。この真ん丸な体がたまらないですね!思わず掴みたくなってしまうほどです。 世の中はシマエナガグッズで溢れていますが、より身近な存在のエナガのグッズが増えてくれたら嬉しいのに・・! 突然、「チリリリリ」と甲高い声で鳴き交わし、すっと動きを止めました。上空にはハイタカ。さすが目がいいな
Dec 21, 2025


木の皮が・・
12月18日、巡回清掃で堀之内東山方面の公園緑地を廻ってきました。足もとからトラツグミが飛んでいきました。 ところで、先日の講座で撮影したこちらの写真をご覧下さい。大きなクヌギのゴツゴツした樹皮を写した一枚です。 じつはこの写真の中に、1匹の生きものが隠れています。まずはノーヒントで。写真を拡大して探してみて下さい! もう少しアップにしてみます。これでわかれば、あなたは素晴らしい観察眼の持ち主です。ヒントはある昆虫です。 ここまで拡大すればさすがに見えますでしょうか。真ん中やや左に、その名もキノカワガという蛾の一種がいます。 これまで、様々な昆虫の擬態を見て、そのたびに感激してきましたが、こちらのキノカワガはかなりの衝撃でした! 成虫という無防備に近い姿で越冬するキノカワガ。樹皮に張り付いていることで小鳥の目を掻い潜っているのです。 体や翅の模様はもちろん、凹凸まで、背景の樹皮とそっくりです。最初、クヌギカメムシの卵でもないだろうかと、 何人かでこのクヌギを観察し始めたのですが、講座の参加者の一人がじっと身を潜めるキノカワガの存在に気付き、...
Dec 21, 2025
bottom of page
