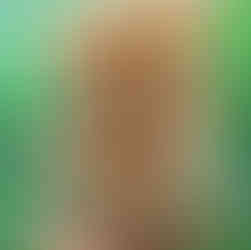アオテンマ
- ひとまちみどり由木
- 2024年6月3日
- 読了時間: 2分
5月31日、朝から雨模様でしたが、天候回復を願って斜面緑地の調査に出かけました。
民有地のため詳しい場所は伏せますが、北浅川の流域に位置する小さな平地林です。
予想通り、アオテンマ(オニノヤガラの品種)が咲いていました。こんなに背高のっぽの
植物は周りに無いので、雑木林の林床ではとてもよく目立ちます。普通のオニノヤガラは
茶色っぽいのですが、アオテンマは全体が薄萌黄色になり、まるで別人のように見えます。
こちらはそばに咲き残っていたオニノヤガラです。色以外に違いは見当たりませんね。
菌従属栄養型の野生ランで、発芽時にはクヌギタケ菌、成長時にはナラタケ菌にそれぞれ
寄生することで栄養を獲得して生きています。光合成のための葉は持ち合わせていません。
そうした生態もあって、主に薪炭林として管理されてきたコナラ・クヌギ主体の雑木林で
見かけることの多い種類です。とはいえ雑木林ならどこでも見られるというわけではなく、
アオテンマもオニノヤガラも、発生する場所がやや限られている希少な植物といえます。
第一の目的であったアオテンマとオニノヤガラとの再会にほっとしつつ、周囲の植物も
全て記録を取りました。途中、足もとからキジが飛び立ってドキッとさせられました・・
写真は順に、ジュズスゲ、ママコノシリヌグイ、ハナウド。河畔林的な植生が主体です。
ハナウドの果実では、某サッカーチームのユニフォームそっくりの柄のアカスジカメムシが
交尾していました。ハナウドをはじめ、セリ科植物の花の蜜や種子の汁を食べる種類です。
雨は上がったものの、甲虫はまだ活動し始めておらず、この子たちが慰めてくれました。
調査から戻り、一仕事終えて自然館を出ると、会議室前のウッドデッキ手すり上に何かが
止まっているのが目に入りました。・・あれ!??・・この色と形はまさかタマムシ類!
なんと先日に続き、またしてもマスダクロホシタマムシに出会うことができました!
辺りはすでに薄暗くなっていて、思うように撮れませんでしたが、本物はずっと綺麗です。
最近、“会いたいな~”とぼやいていたクロホシタマムシとマスダクロホシタマムシに、
3日続けて遭遇することになろうとは、思いもしませんでした。想いが届いたのかも?